
These Foolish Things
フェリーが歌う名曲の数々、まあ、この人の歌い方は真似できないから、こうなるのでしょうけど、女性コーラスやギターの使い方はさすがです、後のBoys and Girlsまで一貫性があると思います。このアルバムでロキシー自体の評価も高まったと思うのですがどうでしょうか。デュランからビーチボーイス、ジャズのスタンダードまでフェリー流です。原曲のエッセンスはそのままに自己流で歌うことのできる数少ない、個性派ボーカリストをフルに発揮しています。この人にデュランではなく、HollandーDozier-HollandやOtis Reddingの曲を歌って欲しいと思っている人は多いと思います。カバーアルバムとしては傑作です。

プレミアム~ザ・ドライヴィング・ヒッツ
テンポの軽い曲やビートの効いた曲が多いので、とても聞きやすく、気分の良くなるCDです。
個々の曲では、ほかのCDではほとんど見ない4番、逆に大変ポピュラーな6番10番11番、クイーンのカヴァーである3番、バナナラマや長山洋子がカヴァーした5番、この曲以外にも大ヒットを飛ばしてるデュランの12番などがお勧めです。
ただ、1番が・・・。
大好きな曲なんですが、このCDでは尻切れ気味に終わるのがいただけない。せっかくだからもう少しアレンジしてほしかった。なお、2001年に出たRadio Editが「Now Best Returns」に収録されてます。

Boys & Girls
本作は、ロキシー・ミュージックがアヴァロンというとてつもない作品で頂点を極め、解散状態になった後、85年に発表されたブライアン・フェリーのソロ作品。アヴァロンの音作りを承継・発展させ、多彩なミュージシャン(マーク・ノップラーやデヴィッド・ギルモアも参加している)のサポートを得て完成させた作品だから、悪かろうはずがない。この頃のブライアン・フェリーは傑作を連発して絶好調という感じですね。本作を代表する曲はやはり「スレイヴ・トゥ・ラヴ」。映画ナイン・ハーフでフィーチャーされ、その思い出が強烈に今でも体に残っていますが、ナイン・ハーフと切り離してもフェリーを代表する、そしてフェリーらしい名曲中の名曲であることは誰にとっても明らかでしょう。この素晴らしい1曲のためだけに本作を買っても損はしません。
本紙ジャケ・シリーズの他の多くの作品と同じく、本作でも歌詞のLP時代の訳とCD時代の訳を読めるが、両者は随分違う。1曲目の冒頭の旧訳は「指一本触れた覚えはない とてもそんな気にはなれなかった」であるのに対し新訳は「触れられるとは思えなかったから 必要性を感じていなかったんだ 勇気というものを、ね」でニュアンスが異なる。言葉をそぎ落としたフェリーの歌詞の抽象性が異なる解釈を生み出す一因と思うが、両方の訳に一長一短があるので、英詞、両方の訳を照らし合わせて、自分の納得する歌詞の訳を見つけるべきでしょう。

プルートで朝食を [DVD]
破壊されるミラーボールと共に飛び散る現実や、溜め息の出るような色彩で捉えられた母の後姿などを綴れ折のようなリズムの中に描き込み、アイデンティティー(自我同一性)を求めてプルート(冥王星あるいは冥府)を目指す旅は、人間の狂おしいまでの性(さが)を描いて神話的ですらある。
二ール・ジョーダン監督による本作は、飛び交う二羽の駒鳥のおしゃべりによって幕を開け、愛されるのが困難な状況にもかかわらず「愛されたい」という主人公の性(さが)を軸に、可笑しくも切ない母を求める旅が描かれていく。ただし、その性は見かけとは裏腹に、IRA(アイルランド共和軍)の爆弾テロや英国警察の暴力や、主人公に対する排斥的な差別という次元を超えてはるかにラディカルな意味を持つ。
さらに、この作品はスクリーンと観る者との間に安易な共鳴を許さない独特の距離感を漂わすが、それはブレヒト的異化効果のような方法論的なものではなく、理論よりも感情に直達する作用をもつ。感動の理由を言語化する作業を飛び越えて、映像自体から直達的に胸を掻きむしられる感覚が先行する。それほどまでに本作は、アイデンティティー探求の深遠さと困難さを、ジェンダー(社会的・文化的なレベルでの性別)すらも超越した根源的な視点から描き切っている。選び抜かれた言葉がちりばめられた脚本(未公開となったジョーダン監督の傑作「ブッチャー・ボーイ」と同じパトリック・マッケイブ原作・共同脚本)と映像と音楽とが融合し、官能的とさえ言える「映画言語」として昇華されている。
Fatherという単語が持つ複合的な意味をも描き出し、秀逸である。そして「今度は女の子をね」と笑みを浮かべる主人公。彼女(彼?)は目指すプルートに辿り着いたのか?
エンドタイトルで流れる“The Windmilles of Your Mind”の歌詞にある風車のように、この映画は未だに私の心の中で回り続けている。
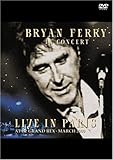
ライヴ・イン・パリ [DVD]
本作は2000年3月のパリでのブライアン・フェリーのソロ・コンサートを記録した傑作と断言してよい作品。フェリーが99年に発表した古いミュージカル等のスタンダード曲をカバーしたソロ・アルバム「As times go by 〜 時の過ぎゆくままに」からの流れで実現した企画だろうが、同作に参加したベテラン・ミュージシャンを含むジャズのビッグ・バンド(といっても十数名ほどだが)と、クラシック弦楽四重奏団+ハープ兼パーカッション担当の計5名の女性ミュージシャンがバックの中核を務めている。フェリーがコンサートで実現したかった編成の非ロック系ミュージシャン達の好サポートを受けて、フェリーが実に気持ちよく歌いまくる。その匂いたつようなフェリー流ダンディズムには酔いしれます。演奏される曲は古いスタンダードばかりでなく、アウト・オブ・ザ・ブルー、オー・イエ、アヴァロン、レッツ・スティック・トゥゲザー、そして最後を締める恋はドラッグ等、ロキシー・ミュージック、またはフェリーのソロ・アルバムから選り抜きの名曲も披露される。そして、これらの曲の原曲の枠を守った演奏がスタンダード曲と並存しても何の違和感もなく、両系統の曲の演奏が組み合わさってパリの華麗な一夜を盛り上げる。このように、本作ではミュージシャン起用、セルフ・カバーを含むアレンジの妙とともに、主人公フェリーが具現するダンディズムの、ある意味一つの頂点といってもよい素晴らしさを十分に堪能できる。収録時間が60分と短いことだけが残念だが、その60分の充実度の高さは並みの音楽DVDの比ではない。






