
韓国人の作法 (集英社新書)
私は、相当な韓国朝鮮オタクを自認する在日日本人であるが、その私も知らない韓国人の作法が幾つかあって目を開かされた。
本書は外国人によく効かれる質問を項目別に分けて編集しているため大変わかり易い。日本て例えて言うと
今時少なくなったかもしれないが「日本では道をサムライが歩いているのか」という古典から、「日本人は毎日寿司を食うのか」
というたぐいの韓国人版質問に答えているのがこの本である。
本書を読んだ感想は「韓国人と日本人は似て非なるもの」ではなく「韓国人と日本人は違うものだが、よく似ているなあ」
というものである。
いくつか本書から拾う。
『韓国人は本当に単一民族か』〜コシアンと呼ばれる東南アジア人とのハーフが増えているらしい。
『韓国人女性はなぜ強烈な原色の服を着るの』これは余り極端な一般化はしてはならない。と著者は言う。
私もそのとおりだと思うが、赤坂のリトルソウルや、本場ソウルの明洞(ミョンドン)を歩く女性
お水系の女性を韓国人女性として一般化するのは、「日本人女性がみんな芸者」と同じ過ちなのである。
『韓国の都市の夜景はどうして赤い十字架で埋め尽くされているのか』
1980年代に訪れた時からたしかにそうなった。世界50大教会のうちの41が韓国にあるのだそうである。
ちなみに韓国のクリスチャンは多くがプロテスタントであるように思うがそうでもなく、内訳を見てみると、
最も信仰者の多い宗教は仏教で22.8%。若干の差でプロテスタント18.3%が続き、以下カトリック10.9%、
儒教0.5%、園(ウォン)仏教0.2%の順となっている。キリスト教信者の多さは、アジアではフィリピンなどとともに際立っている。
プロテスタントとカトリックを合わせると宗教人口の3割近くを占める。
その他0.6%にはイスラム教や天道教、韓国正教会などが含まれるのだそうだ。というのはぼくが余計な知識を披露しました。

ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場 [DVD]
朝鮮戦争での名もなき戦い(ハートブレイク・リッジ=心臓やぶりの丘)を誇りにし、
海兵隊の鬼軍曹としての人生を送るハイウェー(クリント・イーストウッド)。新しい
赴任先で、小隊の訓練をすることになるが、そこは、甘やかされ、落ちこぼれた
若者たちばかりで…。
イーストウッドが、粗野で豪快に、しかし、さりげない人情味を含んだやさしい
タッチも織り交ぜながら描く軍隊ものの佳作。ジョン・フォードの『長い灰色の線』
や「騎兵隊もの」を彷彿させるあたり、また生涯、フォードが愛していた海兵隊を取り
上げているあたりに、イーストウッドのフォードへの私淑も垣間見られる。
苦虫を噛み潰したような顔のハイウェー(イーストウッドは、声も抑え気味で嗄れてい
る演技をしている)と今時の若者たちの感覚のギャップから生まれるユーモアがおもし
ろい。同時に、微細に、そして反復して描かれる訓練シーンによって、若者たちが着実
に成長していき、ハイウェーとの信頼関係も深まっていく過程を示すイーストウッド演
出も手堅い。また、息抜きという感じで数回挿入される、ハイウェーが元妻(マーシャ・
メイスン)とよりを戻そうとするエピソード(女性誌などで、女性の心を掴む記事を読ん
で予習を怠らないのだ!)も、やさしく微笑ましい。豪快なタッチからやさしいタッチへ
の移行が決してチグハグではないのは、自由闊達でいながら繊細なイーストウッド演出
ならではだろう。
DVDは、残念ながら、特典映像などはなく(米国予告編のみ)、本編のみだが、画質
もそれなりに良好であり、初めてのヴィスタ・サイズでの収録なので、イーストウッド・
ファンであれば、持っていたい1枚だ。
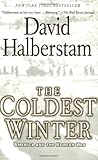
The Coldest Winter: America and the Korean War
私の記憶にある朝鮮戦争とは、敗戦後の日本の復興に寄与した朝鮮動乱景気の印象が強いです。子供の頃、米軍の(横流し?)物資が出回り、 sleeping bagが売られたりしていました。ところが誰かが、あれは朝鮮戦争で戦死した兵士の遺体を詰めて送ったものだ、日本でundertakerが綺麗に処理をしてやるんだ、と言うのです。どうもこれは本当だったようです。そんな体験から本書を読んでみました。筆者の勢力的な取材、資料の精読には感心させられました。マッカーサーの愚かさ、傲慢さ、には驚きました。日本では彼は一種の英雄として記憶されていることに改めて違和感を抱きました。戦争の愚かさ、そして何かを信じて勇敢に戦った兵士たちの霊に敬意を表します。

The Coldest Winter: America and the Korean War
朝鮮戦争を多角的視野から記述。個々の戦闘行動における戦術と指揮官及び下士官の関係などミクロな視点と、米国、ソ連、中国の政治的指導者からみた朝鮮半島の戦略的な意義付けというマクロな視点を交錯させながら、この戦争の全体像を浮かび上がらせる作品。特に、当時の米国政府の内部における権力関係や内政との絡みなどの記述は圧巻。マッカーサーの特異な人間性、アチソン国務長官との確執、トルーマン民主党政権にとっての議会選挙対策としての戦争への関与などの諸点を明らかにするとともに、この戦争の教訓があったにもかかわらず、なぜ米国がベトナム戦争に突入したのか、また、米国民主党政権にとってベトナム戦争からの撤退が政治的に不可能であったのは何故か、というより現代的な問題にも解答を与える。その意味で、米国という国の歴史的及び政治的な本質に迫るもの。この戦争の戦闘行為そのものは、すでに過去のものであるが、現在の朝鮮半島情勢は依然としてその延長にある。東アジアの安全保障環境、米国のアジア戦略などに関心を持つ方には、現在においても依然として極めて有用な視座を与えるであろう。記述が冗長であるという欠点は否定できないが、それを差し引いても、熟読に値する名著と思う。








