
追われる男 (創元推理文庫)
ある国(作中国名は出てきませんが、解説によるとナチスドイツ)の要人(これまた名前は出てこないけど、おそらくはアドルフ・ヒトラー)を狙撃しようとした「わたし」。理由は、政治的なものでもなく正義からでもない。ただ、手強い獲物をしとめたいという、スポーツマンの、ハンターの本能からだけで。しかしこの狙撃は失敗、捕まり激しい拷問をうけながらも何とか祖国のイギリスに帰り着く。が、ここも安全ではなかった。執拗な捜索の手から逃れるため、「わたし」は地位も名誉も投げ捨てて、戦うことを決意する。
追う者と追われる者の、典型的な冒険サスペンス小説です。
前半の拷問の場面や、敵の手から逃れて祖国へ向けて必死に逃げていく姿は、物語の残りの分量からみても捕まって殺されるハズないとは思っていながらも、まさに手に汗握る、迫真の逃避行です。
後半、敵を迎え撃つために都会を離れ、山の中で、穴を掘って住処をつくり、あちこちに罠を仕掛け、といったところは(近くの町に買い物に出たりはするものの)まるで無人島でのサバイバル生活のよう、抜群におもしろい。また、後半にも追いかけっこがあり、これはこれでハラハラドキドキなのですが、それよりも、自分でつくった住処(穴蔵)の中に潜み、追跡者が遠のくまで音も立てずに静かに待っている場面は、追跡劇とは対照的にアクションやスピード感は無いものの、それがかえって緊張感を生み出し、怯えながらジッと待つことの焦燥感が痛いほどに伝わってきて、読んでいて、自分が暗く狭い穴の中に入っているような息苦しささえ感じてしまいます。
本書は、何十年ぶりに新訳で復刊されたのだそう。また、続編もあるとのことなので、ぜひこちらも翻訳出版してほしいものです。

The Remains of the Day (Vintage International)
ふだん、テンポ感のある大衆的な小説を読み慣れていると、
最初は単調な展開に戸惑いを感じた。英国貴族に仕える執事
の物語なんて、現実味に乏しく想像力が及ばなかった。
どうして評価が軒並み高いのだろうか、と、不思
議でもあったのだけれど、ページを追うごとに胸にじんわり
主人公の切なさが染み込んでくる。
人生の夕暮れ時に近づいて、誰でも悔いることや、また、か
なわなかった夢に、苦い感情を抱くことはあるのだろう。
ちょっとした歯車の狂い、ボタンの掛け違え、、、
及びもしない過去を振り返り、あったかもしれない別の人生
を想像してみる。
後半部分、特に、主人公が思いがけないアクシデントがきっ
かけになり出会う人々、そのあたりからの心理描写は秀逸!
最後まで引き込まれるように読んで、深い感銘を受けた。
タイトルの意味は、過ぎ去った一日を振り返ってそのとき目
に入るもろもろのこと、と、訳者のあとがきにある。最後に
夕暮れを比喩にしたメッセージ的な台詞が出てくるが、タイ
トルと微妙に異なる。
是非、あとがきもしっかり読んで欲しい。
あとがきにもあるように、まさに上質の感動を得られる作品
だった。

Children Learn What They Live: Parenting to Inspire Values
私は、ずっと親の言葉に傷つけられて生きてきた。一番身近な人間にそんな目に遭わされたので、人を信じられない人間になった。この本を読んで、自分の親に読んで欲しいと思いましたが、そんな学習能力があったら、そもそも子供に言葉の虐待なんてする訳ないですね。私は、この本を読んで、「自分の親みたいな人間」にだけはならないようにしようと、自分の子供には愛情をもって育てようと思いました。
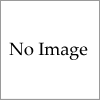
LACQUER&SILVER―Oriental Elegance for Western Tables
~食空間プロデューサー 木村ふみさんが1991年に作られた本です。
英語版の本ですが、写真を見ているだけでもその世界が伝わってきます。
日本の伝統的な器や素材がたいへんスタイリッシュに、
モダンにコーディネートされていて、
まさに「洋のテーブルのためのオリエンタル・エレガンス」。
季節ごとの集いのシーンの設定もさまざまで、
~~
いろいろなスタイルのセッティングを見ることができます。
和の心を感じる粋なテーブルばかりです。
後半には和洋中のテーブルウェアやカラースキームの紹介、
異素材の組み合わせの提案などもあり、
テーブルセッティングの基本を知ることもできます。
良いモノに出会える一冊です。~

英文版 日本茶。 - New Tastes in Green Tea
お茶を使った斬新なレシピがたくさん紹介されているし、写真もとても綺麗で見ているだけでも楽しいです。日本茶の解説なども、詳しく載っていて海外へのお土産にもいいかも。






