
12人の優しい日本人 [DVD]
私事で恐縮ですが、2006年1月21日に大阪のシアター・ドラマシティで、三谷幸喜の最新作「十二人の優しい日本人」を観て来ました。
数多い三谷作品の中でも屈指の傑作だけあって、場内は終始、爆笑の渦、隣で、時にお腹をかかえて笑っている妻の横顔を眺めながら、凄ぶる楽しい舞台と感じながらも、他の観客と、明らかにテンションが違う自分がいました。
何故って?それは、自分は、14年前に、既に同名のこの映画を観てしまっていたからなのですね(笑)。
当時、まだこの日本では議論にも挙がっていなかった陪審員制をモチーフに、日本人の縮図ともいえる12人の"小市民"たちが織りなす、二転三転どころか、五転六転する議論の途方もない逸脱ぶりと、すっ呆けた会話の数々に漂う底知れぬ可笑しさ、それでいて、果たして被告は有罪か無罪か、という法廷劇としてのサスペンスなルーティンもしっかり押さえてあり、存分に映画を楽しんだ後で、三谷幸喜、恐るべしと感じたものです。
今回、舞台を観ながら驚きだったのは、この映画版と、舞台の戯曲のセリフが、ほぼ100%近く一緒だった事。「ラヂオの時間」でも「笑いの大学」でも、過去の傑作舞台を映画化したものが、それなりに映画的に脚色されていた事から考えると、これは意外でした。シチュエーションが一幕物の舞台劇の様な審議室内での話という事もあるのでしょうが、それだけ、三谷が、この"本"に自信を持っているからなのでしょう。
最新舞台での生瀬勝久も好演でしたが、やっぱり、ヘンリー・フォンダにはなれなかった男(笑)、陪審員2号を演じた相島一之(東京サンシャインボーイズのメンバーであり、オリジナルの舞台にも同役柄を演じた)の、時にマゾヒステックなまでの駄々っ子振りは、必見です。
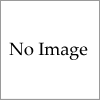
十二人の怒れる男
アメリカ法廷映画史上の最高傑作であることは間違いない!
それよりも特筆すべきは、古い作品にもかかわらず現代社会の病理がそのまま存在している
アメリカ社会の凄さであり、将来的な危惧としての制作陪審員制度に対する問題提起の側面や、
人道や人権という言葉から発せられる誤ったヒューマニズムの脅威という、現代社会において
日常的な問題が随所に盛り込まれている素晴らしい作品であるといえる。

十二人の怒れる男 [DVD]
検察の証拠でっち上げが話題になったばかりだが、ここで12人が議論することは現代でも深刻な問題だ。
特に証言というものは、例えば犯人を見たと言っても、その後作成されたモンタージュこそを犯人の顔と思い込んでしまうらしい。
そこで何人かの容疑者の写真を見せれば、モンタージュにアングルの似ているものや、髪型が似ているものを、確信した顔で「この人が犯人です!」と言ってしまう。
今でも警察や検察は捕まえた容疑者を有罪にするべく証拠を捻じ曲げ続けている。
そして裁判員裁判が始まった今の日本では、法の素人である私たちにその証拠能力を判断せよと言っている。
一つの部屋で行われる12人の男の議論、それもほとんどそこであったことをリアルタイムで感じ取れるようなリアルな作り。
無罪派、有罪派のキャラクターがかなり意図的に振り分けられているような気もするが、まあドキュメンタリーでもないのだからそれもいいだろう。
脚本と演技次第で、名作などいかようにでもなるという素晴らしい実例。

12人の怒れる男 [DVD]
ヘンリー・フォンダ主演のオリジナルとは別物のリメイク作品というふれ込みだったが、ストーリーや人物設定などにかなりの共通点を発見できる。義父を殺し金を奪った容疑で逮捕されたチェチェンの少年を、資本経済転換中のロシア人陪審員が審議するというお話。少年の無罪を主張する者がはじめは12人中1人だけだったのが、審議を重ねていくうちに無罪信奉者が一人また一人と増えていく展開はオリジナルとまったくおんなじだ。
ただし、その審議の進め方がアメリカとロシアではかなり違っている(かのように描かれている)。あくまでも法にのっとりロジカルに反対派の主張を退けていったオリジナルの脚本に対し、本作品は陪審員が各自自分の身の上話をして相手の情に訴えるという、「こんな適当でいいの?」とこちらが心配になるほどアナログな展開が特徴だ。
「感情の入り込むスキのない法治主義はロシアにはなじまない」チェチェン紛争に対するロシア人の複雑な感情を背景に、アメリカ的法治主義に対する批判をチクっと織り交ぜている。共産主義をすっかり過去の異物扱いする資本主義ずれしたロシア人たちの変わり身の早さには今ひとつ釈然としなかったが、新しいロシアを感じさせてくれる1本であることはまちがいないだろう。







